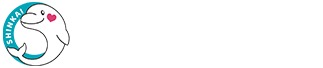胸焼けや吐き気に悩んでいませんか?

- 胸焼けが続く
- 吐き気や嘔吐がある
- 口の中に酸味を感じる
- 酸っぱいものが胃から上がってくる感覚がある(呑酸)
- げっぷが頻繁に出る
- 喉に違和感がある
- 胸や背中に痛みがある など
胸焼け・吐き気の原因
胸焼けは胃酸や消化液が食道に逆流することで起こり、吐き気は胃の運動や消化機能の低下によって引き起こされます。これらの症状には暴飲暴食、ストレスなどの生活習慣のほか、感染症、薬の副作用、自律神経の乱れなど多くの要因が関係します。また、便秘による腸内圧の上昇や、女性ホルモンのバランスの乱れなども原因となることがあります。
症状のみで原因を特定するのは難しい場合も多いので、頻繁な胸焼け・吐き気にお困りの方は、豊中市・庄内・服部天神・三国から通院しやすい庄内駅前しんかい内科・消化器内科クリニックへお気軽にご相談ください。
考えられる病気
ピロリ菌感染症
胃の粘膜にすみつく細菌による感染症です。多くは幼少期に感染し、胃炎(慢性胃炎)や胃潰瘍の原因となります。感染が長期間続くと胃・十二指腸潰瘍や胃がんのリスクを高めてしまいます。
食道がん
食道の粘膜から発生する悪性腫瘍です。初期は症状が乏しいものの、進行すると食べ物のつかえ感や胸焼け、嚥下困難などが現れます。喫煙や飲酒が主なリスク因子とされています。
逆流性食道炎
胃酸が食道に逆流することで、食道粘膜に炎症が起きる病気です。胸焼けや呑酸、胸の痛みなどが特徴的で、食後や横になった時に症状が悪化します。
バレット食道
長期の逆流性食道炎により、食道下部の粘膜が胃の粘膜に置き換わった状態です。自覚症状は少ないものの、胃食道接合部がんのリスクが高まるため注意が必要です。
胃がん
胃の粘膜から発生する悪性腫瘍です。初期は無症状ですが、進行すると胃の不快感や食欲不振、体重減少などが現れます。ピロリ菌感染が主なリスク因子です。
胃炎
胃の粘膜に起きた炎症の総称です。原因は様々ですが、いずれもみぞおちの痛みや胃もたれ、胸焼け、吐き気などの症状が現れます。急性のものと慢性のものがあり、特に後者は胃がんのリスク因子となります。
胃・十二指腸潰瘍
胃や十二指腸の粘膜に潰瘍(深い傷)ができる病気です。ピロリ菌感染や特定の薬物使用が主な原因で、食事前後に現れるみぞおちの痛みのほか、胸焼け、吐き気などの症状を引き起こします。
機能性ディスペプシア
器質的な異常がないにもかかわらず、胃の不快症状が持続する機能性疾患です。ストレスや自律神経の乱れが関係するとされています。
胃腸炎
ウイルスや細菌による感染で起こる消化管の炎症です。突然の吐き気や嘔吐、下痢、発熱などの症状が特徴的です。急性疾患の1つで、多くは短期間で自然治癒します。
胆のう炎
胆管の閉塞や細菌感染により、胆のうに炎症が起きる病気です。右上腹部の痛みや発熱、嘔吐などの症状が現れます。
膵炎
膵臓に炎症が起きる病気です。アルコールの過剰摂取や胆石症などが原因となり、上腹部の激しい痛みや嘔吐、発熱などを引き起こします。
胸焼け・吐き気の診察の流れ
STEP1
問診・診察
- まずは医師による詳しい問診と診察を行い、痛みの場所や性質、時間帯、食事との関連性などについて詳しくお伺いします。
- また、お腹を実際に触診して痛みの部位や程度を確認し、聴診器で腸の動きも確認します。この段階で得られた胸焼けや吐き気の症状について、いつから始まったのか、どのような時に悪化するのか、食事との関係はあるのかなど、詳しくお伺いします。
- また、喫煙や飲酒の習慣、服用中のお薬、ストレス状況なども確認します。症状の性質と患者様の生活環境を総合的に判断し、適切な検査方法を選択いたします。
STEP2
検査
- はじめに血液検査で炎症反応や貧血の有無などを確認し、必要に応じて腹部超音波検査で胆のうや膵臓などの状態を観察します。
- 症状が続く場合や、より詳しい検査が必要な場合は、胃カメラ検査を行います。
- 胃カメラ検査では食道・胃・十二指腸の粘膜の状態を直接確認でき、より正確な診断が可能です。
- 内視鏡検査では当日の絶食や下剤の服用などの事前準備が必要となりますので、改めて検査のご予約をお取りいただきます。ただし、緊急の場合にはその限りではありません。
STEP3
診断・治療
- 検査結果から症状の原因を特定し、適切な治療を開始します。
- 制酸薬や消化管運動改善薬による薬物療法が主体となりますが、症状の原因に応じて食事内容の見直しや生活習慣の改善もアドバイスいたします。
- また、定期的な経過観察により、治療効果を確認しながら、より良い治療方針を検討していきます。